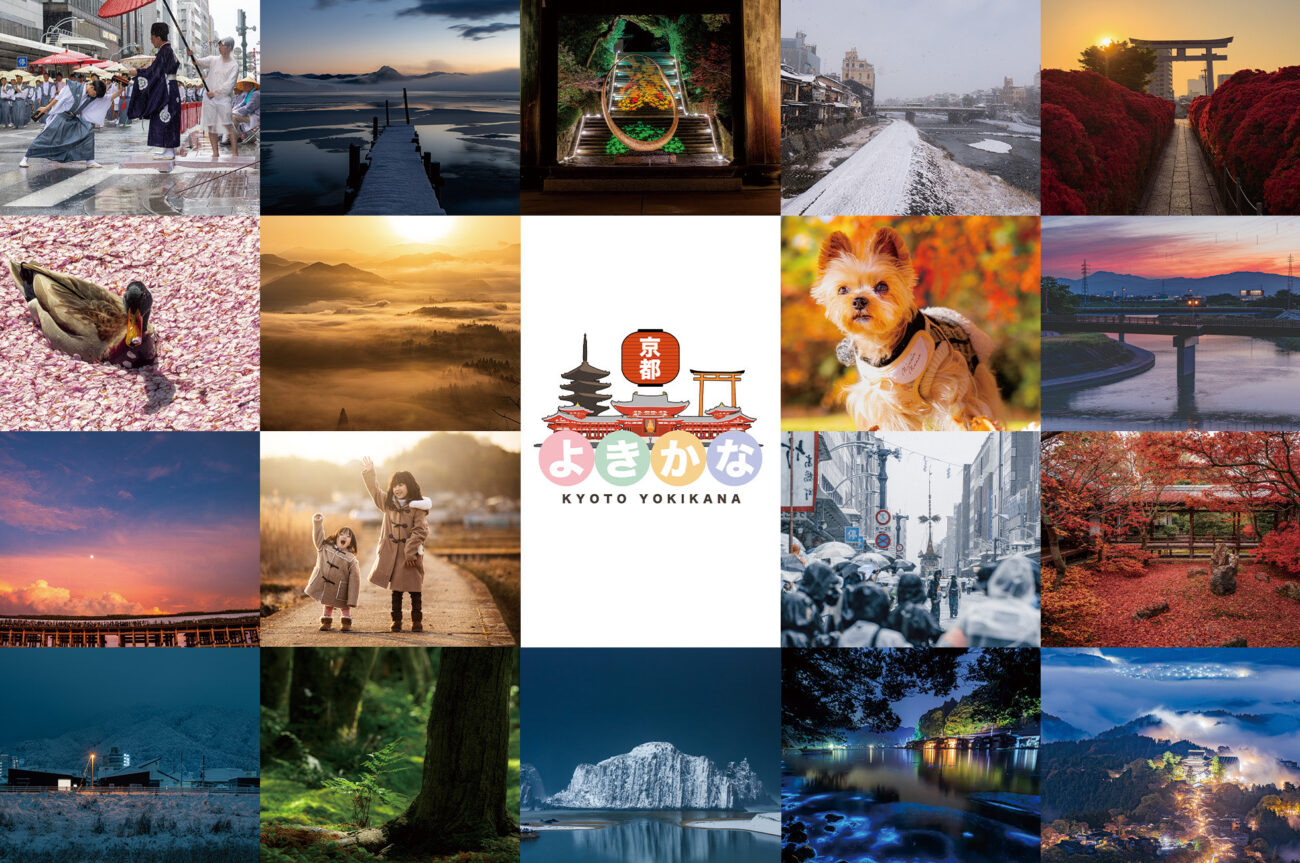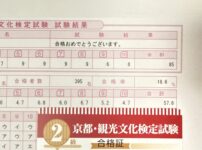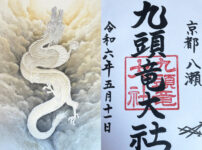橋弁慶山

五条大橋での弁慶と牛若丸の戦いの光景を表現している。
懸装品には下鴨神社・上賀茂神社の葵祭の様子を描写したものがある。
舁山唯一のくじ取らず、舁初めが行われるという特徴がある。
北観音山

くじ取らずの山。
1353年に創設された当時は舁山だったが、曳山に変わったという経緯がある。
山に特有の松には尾長鳥が飾られている。
江戸時代から2014年までは鳩が飾られていたのだが、本当は1757年の記録の尾長鳥が正しいものであり、長い間勘違いをしていたらしい。
松は二本の松を「松取式」を経て南観音山と分けて使用している。
南観音山

宵山の深夜の「あばれ観音」で知られている。
御神体の楊柳観音と善財童子が新町通を3周回る儀式で、起源は不明。
鷹山

江戸時代後期の1826年に暴風雨で山が壊れて以来、休み山となっていたが、2022年に196年振りに巡行に復帰。
御神体は鷹匠、犬飼、樽負。
大船鉾

1864年の蛤門の変で焼失し、長らく休み山となっていたが2014年に150年振りに復興。
くじ取らずで、後祭の最後尾を巡行する。
役行者山

修験道の開祖である役行者をお祀りしている。
山には役行者、一言主神、葛城神の3体が祀られている。
巡行前日には修験宗総本山の聖護院から来た山伏による護摩焚き供養が行われる。
巡行には聖護院の山伏が加わり、ほら貝と錫杖の音が響き渡る。
黒主山

謡曲「志賀」にちなんだ山で六歌仙の一人、大伴黒主が桜を見上げている姿を表現している。
鯉山

中国黄河の龍門の滝を鯉が登りきると龍になったという故事に基づいている。
滝の奥の神社には素戔嗚尊が祀られている。
浄妙山

平家物語の橋合戦が由来。
宇治川の合戦で一来法師が三井寺の僧兵の頭上を飛び越えて敵陣に到達する瞬間を表現している。
飛び越えられた僧兵の名が筒井浄妙だったことから浄妙山になった。
曳山だが松ではなく、宇治川の川岸を示す柳がつけられている。
鈴鹿山

悪鬼を退治した鈴鹿権現を御神体としている。
山の後ろには討ち取った鬼の首を象徴する赤熊、杉の木は鈴鹿の山を表現している。
八幡山

純金箔の祠を乗せて巡行する。
下京区にあった若宮八幡宮が東山五条に移された後に分詞したものと言われている。