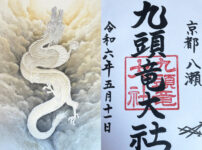京都検定に出題される範囲として、五花街と呼ばれる花街に関する問題が度々出題される。
一般的には舞妓・芸妓としてひとくくりに捉えてしまうが、芸舞妓にも所属する花街が異なり、流派や活動地域が異なる。
今回は、京都検定公式テキストに掲載されている部分の要点をまとめた記事になる。
五花街
現在は下記の五花街が栄えているがかつては島原という地域にも花街が存在した。
現在は花街としては営業していないが、かつての名残として旧揚屋の角屋と置屋兼茶屋の輪違屋が残る。
| 花街 | 流派 | 春の公演 | 秋の公演 |
|---|---|---|---|
| 祇園甲部 | 井上流 | 都をどり | 温習会 |
| 宮川町 | 若柳流 | 京をどり | みずゑ会 |
| 先斗町 | 尾上流 | 鴨川をどり | 水明会 |
| 上七軒 | 花柳流 | 北野をどり | 寿会 |
| 祇園東 | 藤間流 | なし | 祇園をどり |
花街の主な行事
始業式
新年を迎えた芸舞妓が各花街で集まり、今年一年の精進を誓う行事。
祇園甲部では黒紋付に稲穂の花簪を髪に指し、昨年の売花が多かった芸舞妓に奨励賞が贈られる。
最後に京舞井上流の家元が倭文を舞う。
初寄り
1/13の京舞井上流の稽古始めの日。
新門前通大和大路東入の家元を訪ねお雑煮・初舞いで新年を祝う。
八朔
8/1に日頃お世話になっている本家、得意先に挨拶まわりを行う。
かにかくに祭
祇園白川の辰巳大明神近くにある吉井勇の歌碑の前で、献花や茶の湯の点前の披露が行われる。
かにかくにの由来は、歌碑にある「かにかくに 祇園はこひし 寝る時も 枕のしたを 水のながるう」からきている。
事始め
12/13を1年の区切りとしてこの日から正月の準備を始める。
1年の感謝を込めて本家や得意先への挨拶まわりもある。
京舞井上流家元宅では稽古場に玉椿の軸、鏡餅が飾られる。
季節で変わる花簪
舞妓が髪にさしている花簪には季節を彩るシンボルとして毎月決まった花簪をさすしきたりがある。
1/7の始業式のときは稲穂の簪をさす。
| 1月 | 松竹梅 |
| 2月 | 梅 |
| 3月 | 菜の花 |
| 4月 | 桜 |
| 5月 | 藤 |
| 6月 | 柳 |
| 7月 | 団扇 |
| 8月 | すすき |
| 9月 | 桔梗 |
| 10月 | 菊 |
| 11月 | 紅葉 |
| 12月 | まねき |
舞妓さんから芸妓さんになるまで
舞妓志望の女性はまずは屋形(置屋)と呼ばれる芸舞妓を抱える学生寮のような場所に入る。
屋形では舞妓になるための礼儀作法や京ことば、舞、囃子の修行に励み、その期間は1年間でこの期間を仕込みという。
仕込み期間が終わると晴れて舞妓として実際のお座敷に出ることになり、これを店出しという。店出しの日が決まると、店出しの前にお姐さん芸妓に連れられてお座敷見習いを行うが、この時の舞妓はだらりの帯が短く結ばれている格好のため半だらと呼ばれる。髪型は割れしのぶという髪型で月日が経って髪が伸びてくるとおふくと呼ばれる髪型になる。
舞妓は20歳近くになると、舞妓をやめて一般の女性として社会に出るか、芸妓として自立するか選択することになる。芸妓になった際には赤襟が白襟に変わるため、これを襟変えという。襟変えが近くなると髪型は先笄という髪型になり、この期間は2週間ほどとされる。襟変えのタイミングで先笄が切られて晴れて芸妓になる。