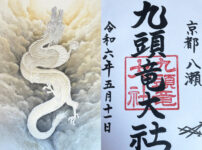長刀鉾

山鉾巡行の順番が予め決まっているくじ取らずの山鉾で前祭の先頭を巡行する。
唯一、生稚児が乗る山鉾で注連縄切りを行う。
鉾先の長刀は疫病邪悪を祓う意味が込められており、かつては平安時代の刀鍛冶である三条鍛治宗近が八坂神社に納めたものを取り付けられていた。
刀の向きは決して神様がいる八坂神社に刃先が向かないように南向きに取り付けられている。
月鉾

月読尊を祀っていることから月鉾と呼ばれている。
最も背が高い山鉾で、稚児人形の名は「おとまろ」
鉾先には三日月があり、装飾は月と水に関係するものが多い。
屋根や浴衣の柄には八咫烏が描かれている。
前懸はインド17世紀のムガール王朝時代のもの。
函谷鉾

くじ取らずの山鉾で、稚児は明治天皇の后の実兄をモデルとした人形の「嘉多丸」を乗せている。
鉾名の由来は、中国の孟しょう君が秦の国に追われて函谷関に差し掛かったとき家来に鶏の鳴き真似をさせて門を開かせ難を逃れたという故事に由来する。
鉾先の三日月と山形で、山の中の闇を表現している。
真木の上部にもうしょうくん、下には鶏が祀られている。
前懸は「イサクに水を供するリベカ」を描いたタペストリーで重要文化財(巡行には複製品を使用)。
鉾の後ろは密教経典や弘法大師の書物由来の文字があることから、鉾自体にキリストと密教が混在していることになる。
鶏鉾

名前の鶏らしさは鉾にはなく、稚児人形にも名前がない。
引き手が頭に被る傘が赤いのは鶏のトサカに由来すると言われている。
天王座には航海の神である住吉明神が祀られている。
後方のタペストリーは16世紀のベルギー製で、叙事詩「イリアス」の一場面を描いたもの。
船鉾

後祭の大船鉾と似ているが、前祭は「出陣船鉾」、後祭は「凱旋船鉾」と呼ばれる。
船鉾の形は軍船をモチーフとしている。
御神体の神巧皇后は今では安産の神として信仰されている。
船首の鳥は想像上の水鳥で、大舵には龍、船体には青海波と龍が描かれている。
木賊山

世阿弥作の謡曲「木賊」が由来の山。
さらわれた子が成長し、父親に会うため信濃へ行き、宿を借りるために話しかけた老人が実は父親であったと気づく話。
山では子をさらわれた老人が木賊を刈る光景を表現している。
綾傘鉾

傘を開いた形をしている。
巡行では棒振り囃子を演奏する。これには疫病退散の願いが込められている。
6人の稚児も歩いて巡行に参加する。
油天神山

名前は油小路綾小路にある天神が由来。
天明の大火後に尽力した風早家伝来の天神像を御神体としている。
山の正面に鳥居、社殿に紅梅がある。
群青色の空に鷹が舞う姿を描いた「翔鷹千花図」が描かれている。
伯牙山

琴の達人である伯牙が友人の死を嘆き、琴の弦を切って二度と琴を弾かなかったという中国の故事が由来。
伯牙が琴を壊そうとマサカリを手にしている光景を山で表現している。
懸装品は全てが中国にちなんだものを使用している。
蟷螂山

屋根にかまきりを乗せていることから「かまきりやま」として親しまれている。
このかまきりは車輪に合わせて顔を傾けたり羽根を広げたりするからくりがある。
南北朝時代、公卿が足利軍に「蟷螂の斧」のような戦いを挑み戦死したことを恨み、1376年に公卿の御所車に蟷螂を乗せて巡行したことが始まりとされる。
放下鉾

鉾先は「洲浜」とも言われており、日、月、星が下界を照らす光景を表現している。
真木中央の天王座と呼ばれる場所に「放下僧」という技芸に秀でた僧を祀っていることから芸事に関係が深い。
稚児人形は「三光丸」という名前で巡行時に稚児舞が行われる。
懸装品には「バグダッド」という羽根を広げた白いフクロウが描かれている。
岩戸山

くじ取らずの山鉾で22番目に巡行する。
見た目は長刀鉾や函谷鉾のような形ですが、屋根に松があるため曳山に分類される。
御神体は天照大神と手力雄尊、伊奘諾尊の三体。
伊奘諾尊は巡行時に屋根に乗る。御神体が屋根に乗るのは岩戸山が唯一。
山伏山

平安時代の浄蔵貴所が、八坂の塔の傾きを特殊な能力で元に戻したり、亡き父を蘇らせたという話が伝えられている。
孟宗山

筍山とも呼ばれる。
中国の史話「二十四孝」由来で、親孝行の孟宗が病気の老母に好物の筍を食べさせたい一心で、真冬に筍を掘り当てた光景を表現している。
この筍を食べた老母は病が治ったそうです。
松についている綿は真冬の雪を表現したもので、粽にも綿があしらわれている。
太子山

聖徳太子を祀る山で松ではなく杉を立てている。
四天王寺建立のため自ら杉の木を伐った話に由来する。
巡行には山の後に荷茶屋が続く。
聖徳太子ゆかりの山なのでお守りは知恵や学業に関するものが授与される。
保昌山

和泉式部に恋した平井保昌が御所の紅梅を手折ってくる光景を表現している。
平井保昌は大江山で酒呑童子を退治したと伝えられている武将で御神体にも鎧がつけられている。
縁結びにご利益があり、女性に人気が高い。
芦刈山

世阿弥作と伝わる謡曲の「芦刈」が由来の山。
妻と離れた男が難波の浦で草を刈っていたところ、京都にでて裕福になった妻が戻ってきたという話が原作。
御神体の人形である男はまだ妻に会えず、芦を刈って苦労している時期の光景を表現している。
四条傘鉾

歴史は応仁の乱以前までさかのぼる。
御神体として使われる若松には赤松が使われる。
棒振り踊りは休み山の時代に失われたものが復活した。
郭巨山

中国の史話、「郭巨釜堀り」に基づいた山
老母と子供を養えなくなったため、子供を犠牲にするための穴を掘っていたところ黄金の釜が出てきたため救われるという話。そのため金運のお守りが授与される。
霰天神山

1504年から1520年の間に京都で大火事があった際、霰が降って火がおさまったことに由来する。
そのことからお守りは雷除け、火除けのものがある。
この山の町は大火の被害に一度も遭っていないと伝えられている。
タペストリーは16世紀のベルギー製で、叙事詩「イリアス」の一場面を描いたもので、鶏鉾のものと元は一枚だったと言われている。
占出山

日本書紀の神功皇后に物語に基づいている。
他の山と違い黒松を使っているには御神体が女性だから。
佐賀県唐津で鮎を釣って戦勝の兆しとした話を山で表現している。
釣りで占いをしていることから「占出山」となった。
菊水鉾

町内の菊水井ゆかりの鉾で、菊水井は室町時代に千利休の師である武野紹鸚の茶亭にあったと言われている。
7月13日から16日にかけてお茶席が設けられ、巡行でも荷茶屋が従う。
菊水の名は中国の故事、「菊の葉より滴る露を飲み長寿を得た」に由来する。
鉾は蛤御門の変で焼失し、1952年に復興した。
2016年には懸装品の七福神が揃い踏みした。
屋根は唯一唐破風屋根をもっている。
白楽天山

中国の詩人、白楽天が道林善禅師に仏法の大意を問う光景を表現している。
タペストリーはヨーロッパのものを何枚も飾り、前懸にはイリアスのトロイア戦争の場面をモチーフに、後方には北京の庭園が描かれている。学問に関するお守りが多い。