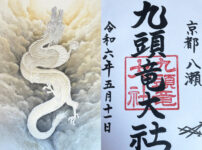今回は京都検定対策の記事です。特に2級以上受験の方におすすめの記事となり、公式テキストには記載の無い範囲まで紹介しています。
京都の有名な桜スポットと言えば、醍醐寺、仁和寺、円山公園、蹴上インクラインあたりが知名度が高く、地元民も観光客も殺到する場所になります。
一般的に桜といえばオーソドックスなソメイヨシノになるのですが、少し品種が違ったり、色や咲く時期が違ったり、固有名称があったりと、特殊な事情を持つ桜も京都にはたくさんあります。
公式テキストに記載のある桜と、テキストには記載が無く、もしかしたら2級以上で出題可能性がある桜を今回はピックアップして紹介します。
下記に桜の固有名称、場所、天然記念物に該当するか、公式テキスト(2025年新版)に記載のあるページをまとめました。
| 名称 | 場所 | 天然記念物 | 該当ページ |
|---|---|---|---|
| 般若桜 | 毘沙門堂 | - | 記載なし |
| 不二桜 | 東寺 | - | 記載なし |
| 御車返しの桜 | 常照皇寺 | - | 記載なし |
| 九重桜 | 常照皇寺 | 国指定 | 431 |
| 普賢象桜 | 千本閻魔堂 | - | 113 |
| おかめ桜 | 長徳寺 | - | 記載なし |
| 御室桜 | 仁和寺 | - | 126 |
| かすみ桜 | 福徳寺 | 市指定 | 431 |
| 鬱金桜 | 六孫王神社 | - | 記載なし |
| 雲珠桜 | 鞍馬山 | - | 311 |
| 関雪桜 | 哲学の道 | - | 379 |
| 千眼桜 | 大原野神社 | - | 記載なし |
般若桜
山科区の毘沙門堂にある般若桜。
宸殿前にある枝垂れ桜のことを指し、地元有志の般若会の皆さんによって手入れされてきたことから般若桜と呼ばれます。
樹齢は約150年で高さは10mほど。現代の般若桜は5代目になります。
不二桜(ふじさくら)

南区の東寺にある不二桜。
拝観エリアに入ってすぐに目の前に現れる紅枝垂れ桜のことを指します。
樹齢は130年超。平成18年に三重県より移植されました。
不二桜と五重塔をセットにした撮影スポットは東寺のシンボル的存在になっています。
御車返しの桜(みくるまがえしの桜)
京都京北ナビより引用
右京区の常照皇寺。
後述の九重桜より遅く桜で、一重と八重の桜が一枝に咲きます。
御車返しの名前の由来は江戸時代の後水尾天皇が、この桜の美しさに何回も車を返して別れを惜しんだということからつけられました。
九重桜(ここのえさくら)
京都京北ナビより引用
右京区の常照皇寺。
光厳上皇による植樹と言われ樹齢は650年超で、京都では唯一の国指定の天然記念物に指定されています。
近年は腐朽が進み、花を咲かす枝が少なくなっているようで、後継木も植えられています。
普賢象桜(ふげんぞう)
千本閻魔堂より引用
上京区の千本閻魔堂(引接寺)にある普賢象桜は遅咲きの八重桜。
花の中心の変わり葉が伸び、それが普賢菩薩がまたがる象の牙や鼻のように見えることから普賢象と呼ばれます。
普賢菩薩について↓
高野山霊宝館より引用
おかめ桜
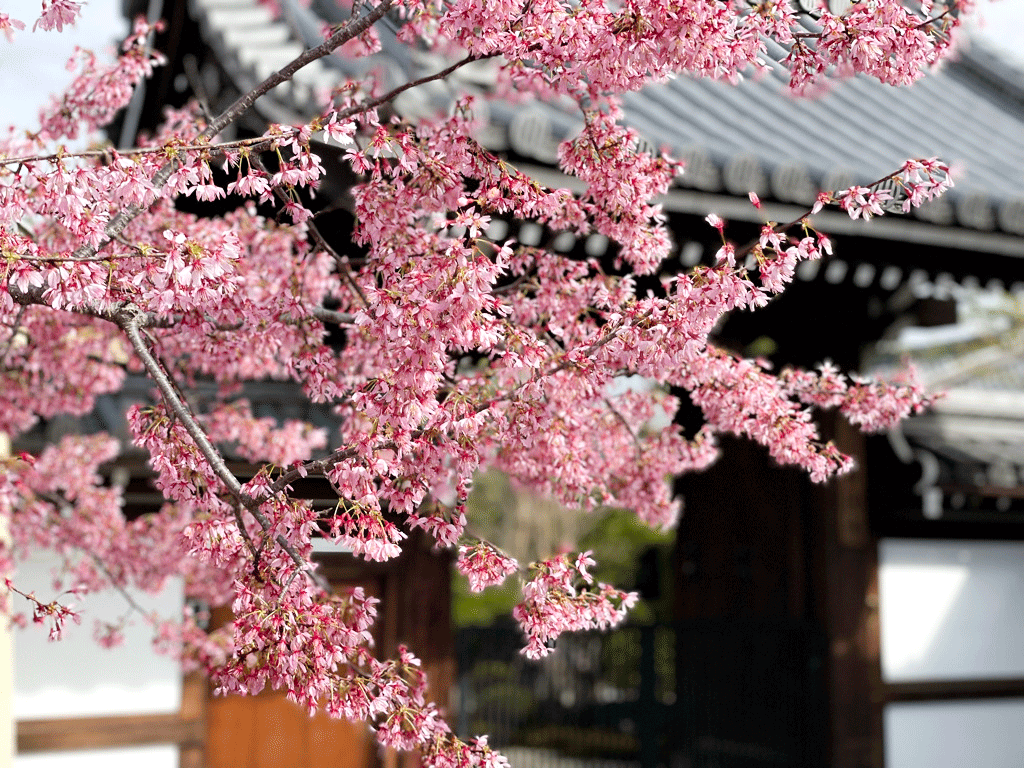
左京区の長徳寺。
イギリス産の品種で、花弁の色がソメイヨシノに比べてかなり紅色が強く、梅の花に近い色合いです。
日本らしい品種名を考えていたところ、日本の「おかめ」という女性から取った説があります。
開花の時期は、京都市では一条戻橋や三条大橋西詰より少し遅く、例年だと3月中旬には満開を迎えます。
御室桜

右京区の仁和寺は御室仁和寺とも言われることから、仁和寺に咲く桜も御室桜と呼ばれます。
「御室」とは天皇の居室の意味があり、仁和寺を創建した宇多天皇がここに造営した御所に由来します。
御室桜は他の桜の開花時期とは異なり、4月下旬が見頃となります。
また背丈も大人の目線と同じくらい低く、その要因は粘土質の土壌で根を深くまで伸ばせないからだと考えられています。
かすみ桜
京都京北ナビより引用
右京区の福徳寺。
樹齢400年の枝垂れ桜をかすみ桜と呼びます。
鬱金桜

南区の六孫王神社は東寺から西に歩いて10分ほど。
鬱金桜は一般的な桜の色とは大きく異なる黄緑色です。
雲珠桜(うずさくら)
日本花の会より引用
雲珠桜は特定の桜のことを指すわけではなく、鞍馬山に咲く桜全体に対しての名称になります。
雲珠とは馬具の飾り金具のことで、常緑の木々の中に点々と白やピンクの桜が咲く光景と似ていることが由来だと言われています。
関雪桜(かんせつざくら)

左京区の哲学の道にある西田幾多郎の石碑周辺に咲く桜を関雪桜と呼びます。
画家の橋本関雪が妻の米子から相談を受け、1921年に寄贈したことが由来です。
哲学の道は熊野若王子神社から銀閣までの琵琶湖疏水沿いの道のことを指し、大正時代に京都帝国大学の西田幾多郎(にしだきたろう)、河上肇(かわかみはじめ)、田辺元(たなべはじめ)らの哲学者が散歩したことに由来します。
千眼桜

長岡遷都の際、奈良の春日大社の祭神を分祀した大原野神社。
千眼桜はたくさんの花芽をつけることから、つけられた名称で満開を迎えて3日で散ってしまうので幻の桜とも言われます。
まとめ
桜の中でもソメイヨシノや枝垂れ桜、河津桜など、京都では多くの品種の桜に出会うことができます。
その品種の中でも特定の地域や場所に咲く桜には固有の名称がつけられ親しまれている場所もあり、京都検定の公式テキストにも一部記載があります。
テキストに記載の桜は当然のこと、2級以上の問題には公式テキストには記載の無いところから出題されることもあるので、今回紹介した固有名称を持つ桜は押さえておくようにしましょう。
もちろん、今回紹介した桜以外にも固有名称を持つ桜はありますのでぜひ能動的に調べてみることで知識の幅が広がります。