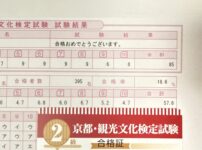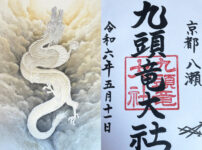2025年の祇園祭、神幸祭においてとてもめでたい話題があった。
それは清々講社第2号、弓矢組の「武者行列」の復活だ。
7/17の神幸祭、7/24の還幸祭では神輿渡御が行われるのだが、鎧兜の姿で神輿の行列の先頭に立ち行列の警護を担う、それが「武者行列」である。
1974年までは武者行列が神輿渡御に参列していたのだが、維持費や人員不足等の問題で以降は参列を取りやめていた。
しかし近年、武者行列復活の声があがり2025年の神幸祭で半世紀ぶりに行列に参列することとなった。
武具自体は行列に参加しなくとも神幸祭に合わせて町内で展示は行われていたのだが、今回は神幸祭前の7月15日に町内会所の弓箭閣で展示されている武具を見に行ってきた。
弓矢町と神幸祭との関わり
弓矢町は建仁寺の少し南、六原学区内にある。
祇園祭では神輿の行列の先頭に立ち、行列を警護する役割の武者行列が存在していたのだが、この集団が住んでいた地が弓矢の製造が盛んだった現在の弓矢町だった。
1721年の記録では90人近くの武者が参列した記録が残っているが、明治以降になると弓矢町内で弓矢や武具を製造する者がいなくなってしまった。
以降、甲冑の修繕や武者行列参列の人員手配などで費用が重なり、町内の財政を圧迫し続けた。
しかし甲冑の劣化や破損の修復に限界を迎え、1974年の神幸祭を最後に武者行列は途絶えてしまった。
それが近年、八坂神社の氏子内で弓矢町武者行列の復活を望む声が高くなり、関係者らの寄付や支援を受け2025年の神幸祭では半世紀ぶりに武者行列が復活することになった。
武具飾り
1947年に武者行列が途絶えた翌年から現存している鎧兜を神幸祭に合わせて、町内会所の弓箭閣と町内の個人宅で一般向けに公開しており、それを「武具飾り」と呼んでいる。
ここで公開されている鉄兜は実際の戦で使われる本物で重量は数10kgにもなる。
実際に神幸祭の行列で身に纏うのは重すぎるかつ、当時の住人とは背丈や体格が微妙に異なることにより、装着が困難だ。
そのため神幸祭では本物の鉄兜ではなく、軽量化した複製品で行列に参加する。


こちらの写真は弓矢町の町内会所である弓箭閣の2階で展示されている武具。
その他の現存する武具は町内の個人宅でも見ることができる。

アクセス

愛宕念仏寺と書かれた石碑が目印。
この石碑の場所を左に進み、突き当たりを右折すると弓箭閣がある。


この建物が弓箭閣
2025年神幸祭の様子

この写真は管理人が宮本組の志丁組(行列ボランティア)として参列していたときの最後の休憩中に来てくれた弓矢組の大将。馬に乗っているのは大将だけで、その他は歩きで参列していた。
管理人は弓矢町のすぐ後ろの行列の中にいたので参列中は姿を見ることがほとんどなかったが、最後に姿を見ることができてよかった。