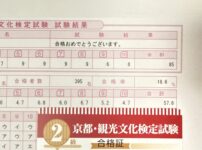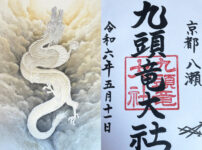京都の寺院を巡っていると、入り口にどーん、と大きな門が出迎えてくれることがよくある。
寺の正面に位置するこの門は三門と呼ばれ、仏道修行で悟りに至る為に透過しなければならない三つの関門(空、無相、無作)を表す。
臨済宗や浄土宗、浄土真宗などの本山クラスの寺院はとくに大きな三門があり、京都では特にその数が多い。
今回は京都において三大三門と呼ばれる代表的な三門について紹介する。
京都三大山門は知恩院、南禅寺、仁和寺のことを指すが、諸説あり東福寺と東本願寺が入る場合もある。
そのため今回は三大三門+東福寺と東本願寺の2箇寺を加えた5箇寺とその高さ・古さをランキング形式で紹介する。
知恩院


浄土宗の総本山で1175年に法然上人が吉水草庵(現在の御影堂)を建てたことが始まり。
現在の広大な土地と伽藍が建てられたのは江戸時代に入ってからのことで、浄土宗宗徒の徳川家康が知恩院を永代菩提所と定め、伽藍の建立は2代将軍の徳川秀忠に引き継がれた。
三門は1621年に建立。高さは24m、横幅50m
| 住所 | 京都市東山区林下町400 |
| 拝観料 | 境内無料 |
| 拝観時間 | 6:00~16:00 |
| 公式ホームページ | https://www.chion-in.or.jp |
南禅寺


臨済宗南禅寺派の総本山で、京都五山(京都市にある格式の高い臨済宗寺院)の別格とされている。
三門の開創は1295年だったが火災で焼失、現存しているのは1628年に再建されたもので高さは22m。
歌舞伎の「楼門五三桐」という演目の中で、石川五右衛門の「絶景かな、絶景かな。」というセリフはこの三門が舞台である。
なお、楼門五三桐が披露されたのは1778年のことで、石川五右衛門が亡くなった後の話であるので、実話ではなくフィクションとされる。
| 住所 | 京都市左京区南禅寺福地町 |
| 拝観料 | 境内無料 |
| 拝観時間 | 12月〜2月 8:40~16:30 3月〜11月 8:40~17:00 |
| 公式ホームページ | https://www.chion-in.or.jp |
仁和寺


真言宗御室派の総本山。
888年に宇多天皇によって創建。897年に宇多天皇が譲位したあとは皇室出身者が住職を務める格式の高い門跡寺院になる。
門正面の左右に阿吽の二王像を安置していることから仁和寺は三門ではなく、二王門と呼ぶ。
応仁の乱で敷地の伽藍のほとんどを焼失したが、二王門は1641年〜1645年の間に再建されたとされ、高さは18.7m
| 住所 | 京都市右京区御室大内33 |
| 拝観料 | 境内無料 |
| 拝観時間 | 9:00~17:00 |
| 公式ホームページ | https://ninnaji.jp |
東本願寺


浄土真宗大谷派の本山。
創建は1602年のことであるが、源流としては1272年に親鸞聖人の門徒が親鸞聖人の遺骨を大谷から円山公園付近に移し廟堂を建て宗祖の影像を安置したことはじまる。
東本願寺は三門ではなく、御影堂門という。
現在の御影堂門は1911年に再建され、高さは27m。
木造の三門としては日本一の高さになる。
| 住所 | 京都市下京区烏丸通七条上る |
| 拝観料 | 無料 |
| 拝観時間 | 3月〜10月 5:50〜17:30 11月〜2月 6:20〜16:30 |
| 公式ホームページ | https://www.higashihonganji.or.jp |
東福寺


臨済宗東福寺派の大本山で京都五山(京都市にある格式の高い臨済宗寺院)の第四位。
摂政九条道家が1236年に祖父・九条兼実の菩提寺として高さ15mの釈迦像を安置する仏殿を建立、奈良の東大寺と興福寺から1文字ずつとり東福寺と称し、完成したのは1255年のこと。
2度の焼失があり、現在の三門は1405年に室町幕府第4代将軍足利義持によって再建。高さは22m
現存する三門では日本最古で最大級、昭和27年に国宝に指定されている。
| 住所 | 京都市東山区本町15丁目778 |
| 拝観料 | 境内無料 |
| 拝観時間 | 4月1日~10月31日まで 9:00~16:00 11月1日~12月 1日まで 8:30~16:00 12月 2日~3月31日まで 9:00~15:30 |
| 公式ホームページ | https://tofukuji.jp |
高さ・古さランキング(上記寺院が対象範囲)
| 順位 | 高さ | 古さ |
|---|---|---|
| 1位 | 東本願寺(27m) | 東福寺(1405年) |
| 2位 | 知恩院 (24m) | 知恩院(1621年) |
| 3位 | 南禅寺(22m)、東福寺(22m) | 南禅寺(1628年) |
| 4位 | - | 仁和寺(1641年〜1645年) |
| 5位 | 仁和寺(18.7m) | 東本願寺(1911年) |