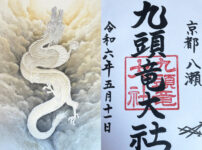京都のお盆は五山送り火、六道珍皇寺などの六道まいり、大谷祖廟の万灯会...など様々な宗教行事が各地の寺で行われます。
8/22と8/23は京の六地蔵めぐりという行事があります。
六地蔵は地獄、飢餓、畜生、修羅、人間、天上の六道と呼ばれる6つの世界で苦しむ人々を救済するために、それぞれの世界に対応した地蔵菩薩像のことを指します。
京の六地蔵は公卿の小野篁の作と伝わる地蔵菩薩像がかつて伏見六地蔵の地に置かれていましたが、これを信仰していた後白河天皇の勅命によって、都の守護、庶民の利益結縁、都に往来する人々の路上安全のために旧街道口(東海道、奈良街道、鳥羽街道、山陰街道、周山街道、若狭街道)に六角堂を建て、地蔵菩薩を1体ずつ分置したことが起源です。
この時勅命を受けたのが平清盛で、実際に分置したのは西光法師です。
以降は、各地に分置された6体の地蔵菩薩をめぐる「六地蔵めぐり」の風習が起こりました。
京の六地蔵の内訳は以下です。
- 徳林庵(山科地蔵、東海道)
- 大善寺(伏見六地蔵、奈良街道)
- 浄禅寺(鳥羽地蔵、鳥羽街道)
- 地蔵寺(桂地蔵、山陰街道)
- 源光寺(常盤地蔵、周山街道)
- 上善寺(鞍馬口地蔵、若狭街道)
京都市内の東西南北に広く分布していますし、電車を使って巡ろうとするとJR、地下鉄、京福電鉄、そしてバス。色んな交通機関を使うことになり、金銭面でも時間的にも不便があります。
そこで管理人は、自転車で巡ることを決意。
なぜなら六地蔵巡りは朝5時から行われているので電車が動く前に行動でき、夏の暑くなる時間の前には全ての箇所を巡ることができ、費用も0円だからです。
朝5時前に家を出発して開門と同時に1つ目の寺でお参りし、暑くなる時間が来る前に6つのお参りを完了させる計画で行ってきましたので、実際のルートや走行距離などをご紹介します。
今回走行した簡易ルートはこちらです。
管理人は東山区の一番北に住んでいるので、スタートは三条白川橋、そして蹴上の山越えをし1箇所目は山科の徳林庵、そこから伏見六地蔵、鳥羽...と時計回りに進めることにしました。
4:42 出発(三条白川橋)
暗闇の中、三条白川橋を出発しました。
5:06 徳林庵(山科地蔵)

三条通を東に進み、山科駅の少し東にあるのが山科地蔵の徳林庵です。東山区から25分程度の走行時間。
徳林庵は1550年に南禅寺の雲英正怡禅師が開創の臨済宗南禅寺派の寺院。
徳林庵の北側に、仁明天皇の第四皇子、人康親王の山荘があったことから、この地は第四皇子が住んでいた四ノ宮と呼ばれていました。
現在の四宮という地名は、この伝えから来ている説と、別説で付近の両羽大明神社に八幡宮、伊邪那岐尊、素戔嗚尊、若宮八幡宮の四柱が合わさって諸羽神社と改称されたことから四ノ宮という地名になったという説もあるようです。
5:36 大善寺(伏見六地蔵)

山科駅から地下鉄沿いに一気に南下して20分ほどにもともと6つの地蔵が安置されていた「伏見六地蔵・大善寺」に到着。
大善寺は705年に藤原鎌足の子、定慧によって創建の浄土宗の寺院。
六地蔵巡り発祥の地でもあるので、大善寺は「六地蔵」の名で親しまれています。
小野篁作の地蔵菩薩立像は重要文化財に指定。
6:18 浄禅寺(鳥羽地蔵)

伏見桃山から竹田、そして鴨川を渡った先にある鳥羽地蔵の浄禅寺。道が複雑なので、頻繁に現在地を照らし合わせながら35分で到着。
浄禅寺は1182年創建の浄土宗西山禅林寺派の寺院。
平安末期の武士・遠藤盛遠が恋した袈裟御前には夫に渡辺左衛門尉源渡がいたため、夫を殺そうとします。
しかし、夫の身代わりとなって妻の袈裟御前を殺すことになってしまい、この罪を恥じた遠藤盛遠は出家し文覚上人となり、袈裟御前の菩提を弔うために浄禅寺を建立しました。
この時の袈裟御前の首塚が恋塚と呼ばれていることから、現在は「恋塚浄禅寺」の名で知られています。
8/22の夜には六斎念仏の奉納が行われます。
6:49 地蔵寺(桂地蔵)

桂川を越えて、桂離宮から西に少しの地蔵寺へ。
地蔵寺は1339年、光厳天皇の勅許を受けた虎関師錬により無関普門(大明国師)の塔所として創建されました。
本堂には鎌倉時代の石像薬師如来を安置しています。
7:16 源光寺(常盤地蔵)

桂川を東に越えて、JR花園駅の近くまで道なりに北上。20分ほどで常盤地蔵・源光寺に到着です。
源光寺は臨済宗天龍寺の末寺で、創建は811年、嵯峨天皇第三皇子である源常(みなもとのときわ)の山荘を寺に改めたものとされてい
常盤の地は源義経の母、常盤御前の生誕の地でもあり、境内には墓があります。
常盤御前は義経記に「日本一の美女である」と記されています。
7:36~8:10 寄り道(円町、上七軒)
朝5時くらいに軽く朝ごはんを食べただけで、長距離を走りましたのでエネルギー補充のためすき家で朝食を食べ、そして最近みた映画国宝のロケ地として登場した上七軒まで寄り道してきました。


8:35 上善寺(鞍馬口地蔵)

最後は鞍馬口の上善寺。
上善寺は863年、円仁により天台密教の道場として創建、1594年に豊臣秀吉の京都改造によって現在の地に移転し、浄土宗に改変されました。
越前松平家は黒印百石を寄進、藩祖・結城秀康公をはじめ歴代藩主の菩提所と定めました。
8/22の夜には六斎念仏の奉納があります。
9:08 帰宅

4:40に自宅を出てから約4時間半、距離にして45kmの六地蔵巡りを無事に終えることができました。
9時過ぎには暑くなりはじめてはいますが、自転車で風を切って走るとそこまで苦ではありません。
汗もそこまで大量にはかいていませんでしたので、水500mlのペットボトル1本分くらいの水分補給で大丈夫でした。